だるい日も、心が整う。脳にやさしい習慣
朝起きても疲れがとれていなくて、
なんとなく身体がだるい
やる気が出ない
集中できない
なぜか気分が落ち込む
といったことはありませんか?
まじめな人ほど
そんな自分を叱責して、無理しがちです。
でも、もしかするとそれは
脳と心が「ちょっと休ませてほしい」と
サインを送っているのかもしれません。
そこで今回は、
がんばらなくても整う、“脳にやさしい習慣”をご紹介します。
だるい日こそ、自分をやさしく扱ってあげましょう。
🧠 なぜ“だるく”なるの?脳と自律神経の関係
「だるい…」と感じるのは、
脳の奥底にある自律神経中枢が関係していると考えられています。
過度な運動や労働、
暑さ、ストレスなどによって
自律神経が酷使されると
自律神経の中枢である
・前帯状回(ぜんたいじょうかい)
・視床下部(ししょうかぶ)
で活性酸素がたくさん出すぎて
活性酸素から細胞を守る抗酸化物質が対応しきれなくなります。
つまり「だるさ」は、
“怠け”ではなく、
脳と神経ががんばりすぎた結果とも言えるのです。
だからこそ、
がんばるより「休ませる」「いたわる」時間が必要なのです。
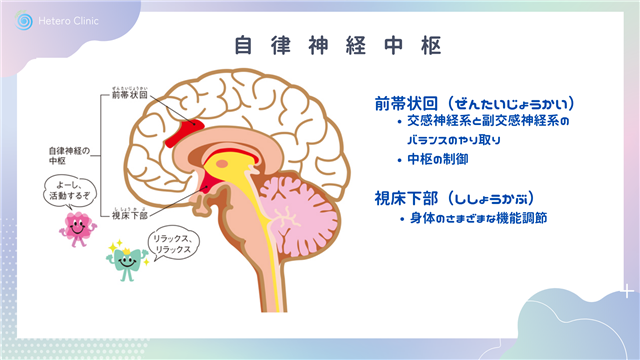
🌿 がんばらなくても整う、脳にやさしい習慣ベスト3
① 1日5分の「何もしない時間」
音を消し、スマホを置き、ただ目を閉じて、深く呼吸するだけ。
この“何もしない時間”に、
脳はDMN(デフォルト・モード・ネットワーク)という
「内省モード」に入ります。
この時、脳は静かに情報を整理し、
過剰な刺激から回復しようとします。
🧘♀️毎日5分でも、続けることで
「脳の呼吸」がスムーズになっていきます。
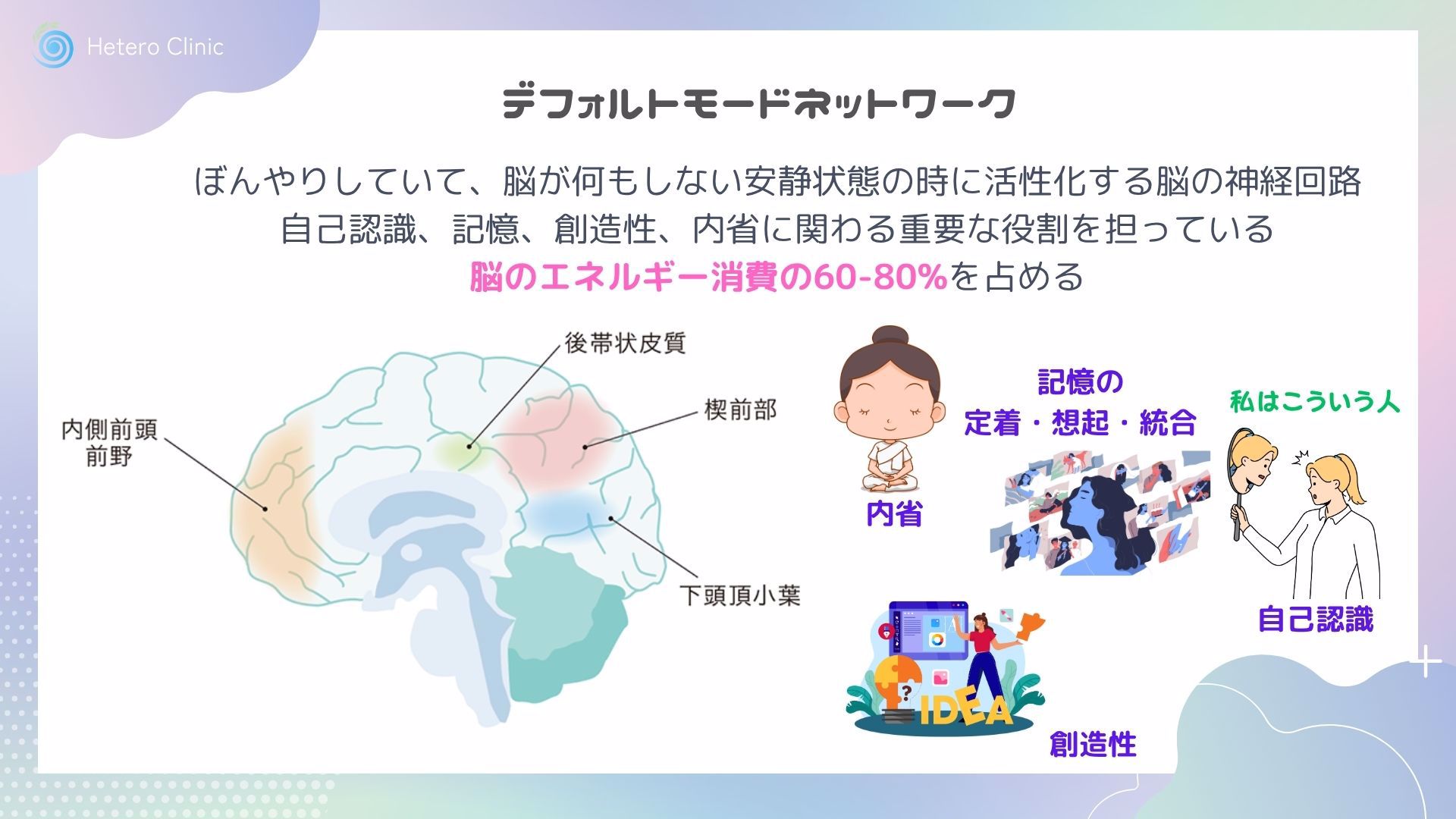
② “感覚を味わう”プチ習慣
疲れているときほど、「五感」を使う時間が脳の癒しになります。
-
手でお湯をすくって感触を感じる
-
香ばしいお茶の香りを吸い込む
-
空を見上げて風の音に耳を澄ます
こうした感覚は、
脳の“今ここ”を感じるネットワーク(前帯状皮質や島皮質)を刺激し、
思考の渦から抜け出すサポートをしてくれます。
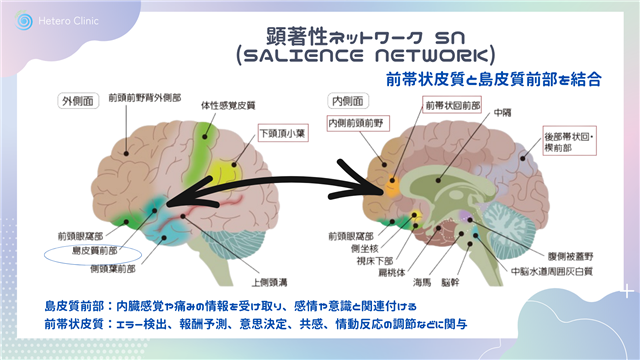
③ “脳に優しい言葉”を自分にかける
脳は、自分の言葉すら「現実」として受け取ると言われています。
「なんでこんなにだるいの」
「またできなかった…」
という言葉は、
知らず知らずのうちに脳のエネルギーを奪ってしまいます。
🌸代わりにこんなふうに声をかけてみてください。
「今日は少しだけ、ゆっくりしよう」
「できたことに目を向けよう」
「今は整える時間だね」
このようなセルフ・コンパッション(自分への思いやり)が、
前向きな神経ネットワークの働きを助けてくれることがわかっています。
逆効果になりやすい“だるさ対処法”に注意
そのやり方、脳をもっと疲れさせていませんか?
「だるい…でも、なんとか動かなきゃ」
そんなとき、
ついやってしまいがちな“がんばる対処法”が、
かえって脳と心をさらに疲れさせることがあります。
ここでは、
よくある3つのNGパターンと、その理由・代替策をご紹介します。
❌ 1. タスクを詰め込む → 脳の処理速度が落ちているときは逆効果
「動けば元気になるかも!」
と無理に予定をこなそうとするのは、要注意。
だるい日というのは、
脳の前頭葉(判断・集中・意欲をつかさどる部分)が、
すでにエネルギー切れを起こしている可能性があります。
そこにさらにタスクを詰め込むと、
処理スピードが落ち、ミスが増えたり、予定通りにいかないことで自己嫌悪に…。
🧠【脳科学的背景】
疲労時は、前頭葉や前帯状皮質の血流が低下し、注意力・実行機能が低下(Mizuno et al., Brain Research, 2014)
🟡代わりに:
「To Doリスト」ではなく
「やらないことリスト」をつくり、ひとつでも減らす。
「ひとつできれば上出来」くらいのマインドで、脳にやさしく。
❌ 2. 甘いものやカフェインで元気を出す→ 一時的に上がって、すぐ下がる
チョコ、菓子パン、甘いドリンク、コーヒー…。
疲れているときほど、
“即効性のあるエネルギー”に手が伸びがちです。
これは血糖値と脳のエネルギーバランスに大きく関係しています。
確かに、
糖質を急激に摂ると血糖値が上がり、脳は「元気になった!」と錯覚します。
しかしその後、血糖値は急降下し、
むしろ“反動でだるさが増す”という悪循環が起こります。
またカフェインは、
疲労物質アデノシンの作用を一時的にブロックしますが、
根本的な回復にはつながりません。
🔍【参考】
・高GI食品による血糖値の乱高下と疲労感の関係(Wolever et al., 2006)
・カフェインはアデノシン受容体を遮断し、
一時的な覚醒作用をもたらすが、
長期的な脳疲労はむしろ増すという報告あり(Nehlig et al., 1992)
🟡代わりに:
低GIのナッツ、ゆで卵、味噌汁などゆるやかにエネルギーになるものを。
カフェインは午後2時以降は控えめにし、
ノンカフェインのハーブティーなどで脳をクールダウン。
❌ 3. SNS・ネットを“なんとなく見る”→ 情報過多で脳がさらに疲れる
「何もする気がしないから、とりあえずスマホでも…」
そんな“なんとなくのスクロール”が、
実は最も脳を疲れさせる行為のひとつ。
SNSやネットニュースからは、
色・音・言葉・感情などの情報が一気に入ってきます。
これをすべて処理しようとする脳は、静かに、でも確実に消耗しています。
📚【研究】
SNSの長時間使用と注意力・感情調整力の低下との関連が報告されている(Twenge et al., 2018)
🟡代わりに:
「見る時間を決める」
「あえて何も見ない5分をつくる」
ことで、脳をクールダウン。
おすすめは、
“目を閉じて呼吸に集中”するだけのマインドフルブレイク。
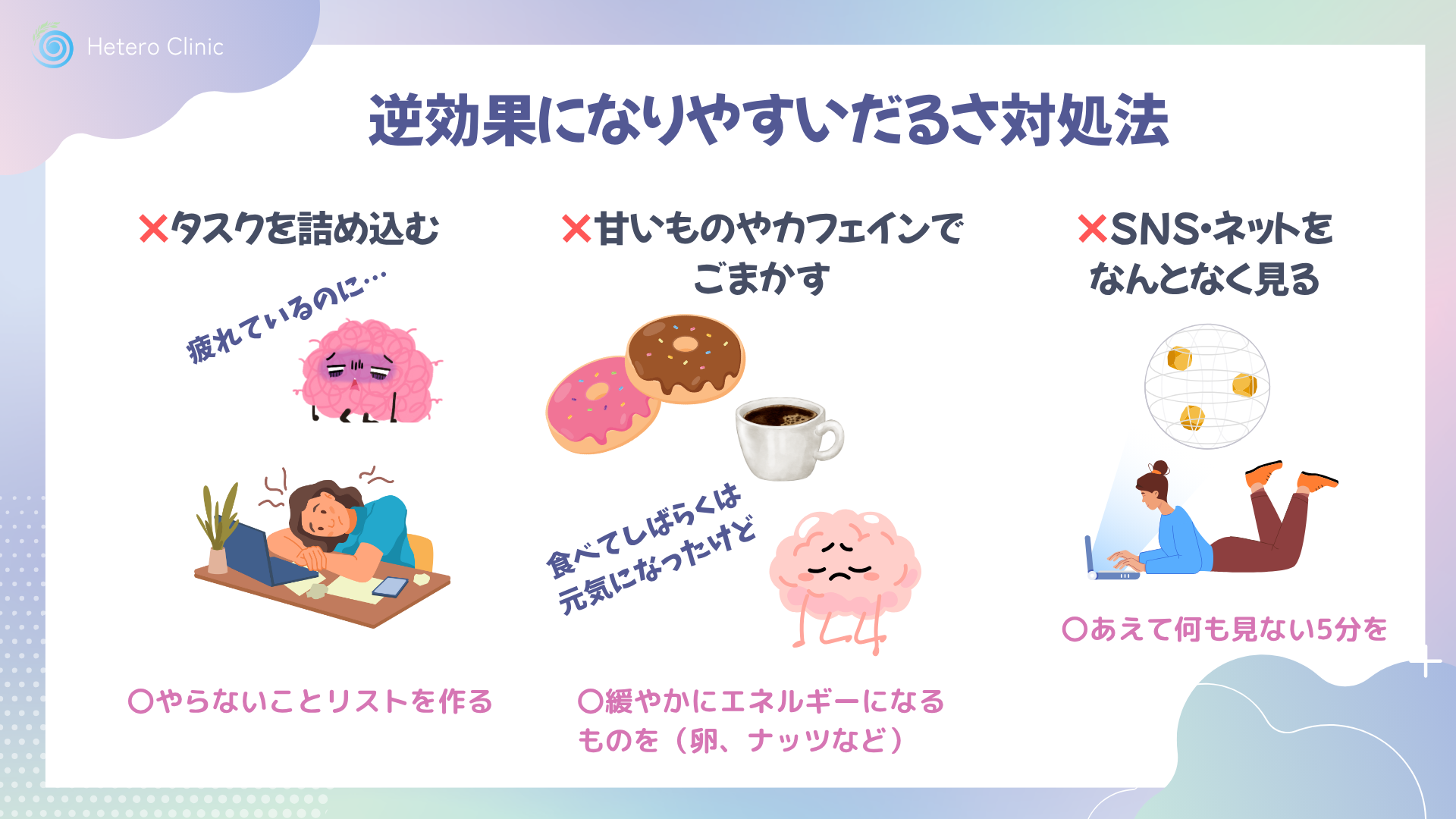
🕊️ 「整える」は、“削る”ことから始まる
だるい日は、
がんばって「何かを足す」より、
「今、脳に負担をかけているものを減らす」ことが最優先です。
予定、情報、刺激、食べ物、人間関係…
少しだけ“引き算”をしてみると、脳は静かに整い始めます。
だるさを責めず、受け入れることが、
結果的に最も効率的な“回復スイッチ”なのです。


