“なんとなく不調”を感じたら、脳にスペースを
「なんだかうまくいかない」そんな日、ありませんか?
☔ 集中できない
☔ 朝がつらい
☔ イライラしやすい
☔ 頭がぼんやりする
病気じゃないけれど、なんとなく調子が悪い。
5月のこの時期、
そんな感覚を抱えている方がとても増えています。
その背景には、
「脳の詰め込みすぎ」=余白不足が隠れていることがあります。
🧠 脳の“余白”がなくなると、なにが起きる?
私たちの脳は毎日、
-
情報
-
感情
-
タスク
-
決断
など、大量の“処理”をし続けています。
脳は“ごちゃごちゃの机の上”のように詰まり、
本来のパフォーマンスを発揮できなくなってしまうのです。
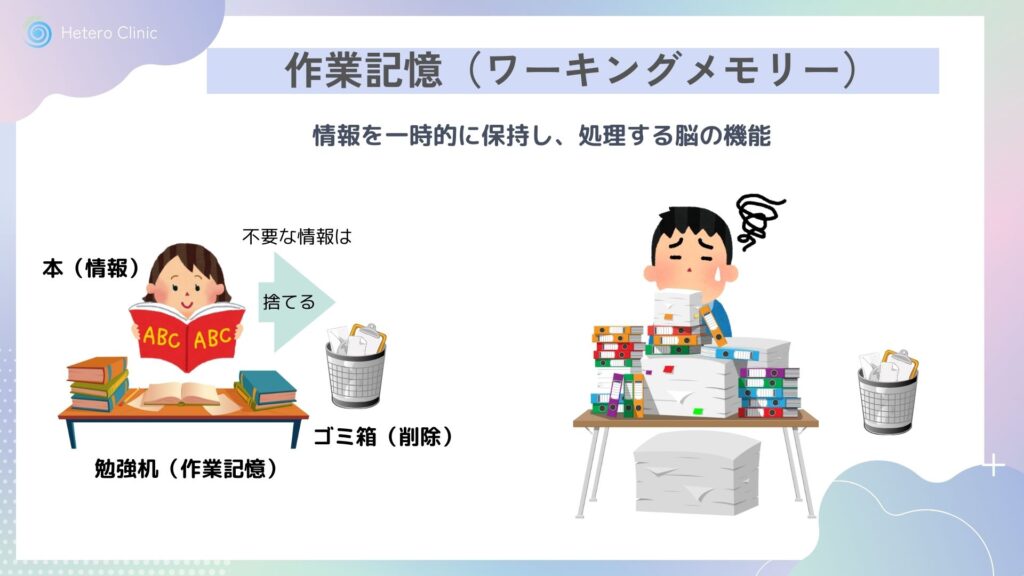
「ちゃんと寝てもスッキリしない」
という“なんとなく不調”の正体かもしれません。
🧠 脳にスペースをつくる優しい3つの習慣
📝 その1. 頭の中を”出してみる”メモ時間
私たちの脳は、
今考えていること・気になっていること・やるべきことなどを、
すべて一時的にワーキングメモリ(作業記憶)で処理しています。
でもこの作業領域には限界があり、
一度に処理できる情報は4±1個程度しかないと言われています【Cowan, 2010】。
▶ メモで「外に出す」=脳の“解放”
頭の中のことを紙に書き出す/言語化することで、
-
情報や感情を一度“外”に出せる
-
いま何を気にしているのか、視覚的に「見える化」される
-
その結果、脳の中にスペースができて、他のことに集中できるようになる
これは、まるでごちゃごちゃの机の上を片づけて、
仕事に集中できるようにするのと同じです。
実は、書き出すことで、
感情が整理され、ストレスが軽減したり
脳の前頭前野が活性化し、冷静な判断をくだしやすくなる
といわれています。
💡実践法
● 時間:3分だけ(タイマーをセットしてもOK)
● 書き方:とにかく思ったことをそのまま
例:
- 今日やらなきゃと思ってること
- なんだか気になること
- 今の自分の気分や体調
- どうでもいいことでもOK(「眠い」「雨降ってる」など)
「うまく書こう」と思わないことがポイントです。
脳の中にスペースをつくるいちばん簡単な方法は、
「考えていることを、いったん紙に出してみる」こと。
書くことは、
思考の整理であり、心の深呼吸でもあるのです。
🧘 その2 「スマホを見ない5分」をつくる
▶ なぜ“見ない”だけで脳が休まるの?
スマートフォンを見る行為は、実は
📲「情報のインプット」+「次に何を選ぶかという意思決定」の連続です。
つまり、
-
脳は常に判断をしながら
-
報酬(いいね・通知)を期待してドーパミンが出たり
-
感情の起伏を受け止め続けている
そんな“絶え間ない刺激”の中に脳がさらされている状態が、
現代人の“当たり前”になっています。

🔬 脳科学で見る「ぼーっとする」ことの重要性
スマホを見ない=何もせずに「ぼーっとする」時間。
このとき働くのが、
脳のデフォルトモード・ネットワーク(DMN)という仕組みです。
▶ デフォルトモード・ネットワーク(DMN)とは?
-
外界への注意が向いていないときに働く、“脳の内側処理ネットワーク”
-
記憶の整理、自己認識、感情の調整、創造性の促進に関係する
📖【参考】Raichle et al., PNAS, 2001
安静時の脳は、
外からの刺激がなくても積極的に「内面の整理」を行っていると報告。
💥 スマホ依存と脳疲労の関係
スマホを頻繁にチェックする人は、
-
ワーキングメモリの能力が低下しやすい(Hadlington, 2015)
-
注意力の持続が短くなる
-
うつ・不安傾向が強くなる傾向がある(Twenge et al., 2017)
といわれています。
特に情報処理力や集中力の高い50代キャリア女性は、
“マルチタスク脳”のままオンとオフの切り替えができず、
知らないうちに疲弊してしまう傾向があります。
🕰 実践のコツ:スマホを見ない「たった5分」のつくり方
- 朝起きてすぐ:ベッドの中で深呼吸3回、スマホを手に取らない
- 通勤・移動中:電車の中で1駅分だけ“スマホ封印”して、窓の景色を見る
- 就寝前:ベッドに入ったら、画面を見ずに今日の感謝を1つ思い出す
情報でいっぱいになった頭を、いったん空にしてあげましょう。
思考も感情も、整理されていくスペースが戻ってきます。
🌿 その3 「やらなくていいこと」を決める
私たちは日々、「やらなきゃ」で頭がいっぱい。
でも実は、
その中には「本当は今やらなくてもいいこと」がたくさん含まれています。
思いきって、「やらないこと」をあえて決めてみる。
それだけで、脳にスペースが戻り、心にも余裕が生まれます。
▶ 本質は“脳の節約術”
現代人の脳は、
毎日35,000回以上の意思決定をしているともいわれています。
中でも50代キャリア女性は、
-
仕事:優先順位・判断・資料チェック・部下対応
-
家庭:献立・家事・家族ケア
-
自分:健康・美容・時間管理
と、
あらゆる場面で“決断疲れ”が蓄積しやすい状況にあります。
🧠 「決断疲れ(decision fatigue)」とは?
-
判断や選択を繰り返すことで、前頭前野が疲弊する現象
-
疲れると、やる気や集中力が低下し、
判断ミスや感情の乱れが起こりやすくなる
📖 Baumeister et al., Journal of Personality and Social Psychology, 1998
意思決定が多い日は、後の行動で衝動的になりやすいという報告も
✅「やらないことリスト」を作るメリット
✍️ 実践ステップ:「やらないことリスト」のつくり方
📌 ステップ①|“気が重いタスク”を書き出す
例:
-
SNSのチェックを毎日しなきゃ
-
毎週の掃除を完璧にしないと
-
毎朝のニュースを全部見ないと
📌 ステップ②|「これは今週、やらなくてOK」に〇をつける
それを「やらないことリスト」としてメモしておくだけでもOK!
たとえば、
・仕事で疲れて家に帰ってすぐに家事をするのがつらいのであれば、
平日は洗濯物をたたまない
・疲れていてもSNSを開いてしまうのであれば、
通知は切って、見る時間を夕方だけにする
📌 ステップ③|週末に振り返ってみる
意外と「やらなくても問題なかった」が多いと気づけます。


